2012年09月13日
僕的考察 1

ちょっと趣を変えてフリーとディスタンスにスポットをあて、僕的に考察してみました
もともとディスタンスプレーヤーを夢見てドッグライフを送るようになり、CONNIEを迎えて嫌々(泣く泣く?)フリースタイルに挑戦した経歴から、
ある意味両方の立場がよく解ります
フリースタイルとディスタンス、日本ではこのような区分けがはっきりされているように思いませんか?
もともとアメリカでディスクドッグが始まり、その始まりはフリースタイルだったはずです
アメリカ、いや世界各国で「ディスクドッグに熱中してます」なんて言うと「トリック見せてくれ」なんて言われるに違いありません
外国の競技会の事情はあまりわかりませんが、フリースタイルとディスタンスを日本のように分けて考えるのではなく、ディスクドッグ
イコール フリースタイルといった認識のようです
1980年代にこのドッグスポーツがアメリカより紹介され、日本の先人たちによりすぐさま競技化されました
今と違い、まだまだディスクドッグの情報も乏しく、動画も手に入りにくい時代だったので写真を見てトリックを研究していたそうです
そんな状態ですからフリースタイルの競技会などエントリーがたくさん集まるはずもありません
そこで、初心者でも十分楽しむことのできるディスタンスを主軸に持っていくことで凄い勢いでこのスポーツが広まっていったようです
そんな流れを引きずってか?未だフリースタイルの愛好者は飛躍的に増えているようにも思えません
どうしてでしょうねぇ~?
そこで僕なりにその理由を考えてみました
①難しい ②めんどくさい ③はずかしい ④教えてくれる人がまわりにいない ⑤ディスタンスがくずれる
ざっとこんな感じでしょうか?
では、ひとつずつ検証してみましょう
①難しい
ですが、見ていると多くの人達は犬の事を無視してしまい、自分のやりたい事からやろうとしてしまいます
人間側にスキルが備わっていないうちに難易度の高いトリックを試した結果、犬達に負荷をかけてしまった
すぐに答えを出そうと思ってしまうあまりにうまくいかない上、犬との信頼関係さえ崩れてしまう、ある意味最悪のパターンです
決して、フリースタイルは難しいことはありません 確かに難しいトリックはたくさんありますが簡単なことからチャレンジしていけばいいんです
今、ボルティングが出来なくてもいいじゃないですか 「出来る事から少しずつ」は、ドッグトレーニングの基本です
少しずつ技のレパートリーが増えて行き、将来必ずルーティーンも作れるようになります
②めんどくさい
これはわかる気がします(笑)
いろんなめんどくささがありますが、まず服が汚れます(大笑)
ある程度計画性をもって取り組む必要があります
やってる人達がどことなくストイックで近寄りがたい雰囲気があります
フリースタイルな人達ってやたらと横文字連発していてめんどくさい
いやいや、本当にめんどくさいですねぇ
でもですね、少しずついろんな事が出来るようになるとめんどくささなんて吹っ飛びますよ
いや本当です!
犬と複数の言葉でやり取りが出来るようになるともはや相手は犬ではなく同類です
こんなこと言ったらディスタンスな人達に叱られるかましれませんが、この感覚はディスタンスだけやってる人達にはわかりずらいと思います
めんどくさがらずに是非出来る事からやってみようじゃありませんか
競技会に出るためとかそんなんじゃなくて、普段の遊びやコミュニケーションのひとつとして取り入れてみるといいんじゃないでしょうか
③はずかしい
これも良くわかりますよ
実は僕も以前は思っていました
余程ナルシーじゃないと人前であんな事出来ないよな~なんて感じに思った事があります(笑)
まして今はやりのドッグダンスのトリックなんかどんな顔してやったらいいんだろ~ってな感じもありました
流石に未だダンスの要素を取り入れることは出来ませんが、これも不思議なもので真剣に取り組んでいくと恥ずかしさも吹っ飛んで行きます
僕の場合、どちらかと言うと「恥かいてなんぼ」って世界になってしまいました
それよりも、あの技が決まったらウケルかなとか真逆の発想に変わっていったように思います
④教えてくれる人が周りにいない
これは仕方ありませんね
第一に取り組んでる人が絶対数少ないんですから
まずは人に頼らないで自分一人で取り組むのがベスト
自分で考え抜いて身に付いたものって大きいのです
ひとつのトリックを犬に教えていく時、基本となるやり方以外にたくさんのやり方、犬と自分に合ったやり方があります
それが成功であろうが失敗であろうが間違いなくその人の経験になります
そしてどうしても行き詰って困った時に、上手な人に競技会なんかで質問してみるといいと思います
自分で経験した上での質問なので質問の意図もはっきり伝わり解決の糸口も見えてくるかもしれません
⑤ディスタンスがくずれる
先日の競技会で聞いた話です
いやいや以前からこのような風潮がありました
フリーをするとディスタンスに悪影響が及ぶ???
まったくありえない話です(笑)
フリーをする人の中にこのような発言をする人はまずいないでしょう
困るのは、こういった風評被害です
どなたが発したとかは問題のないことですが、その人がディスタンスのトッププレーヤーだったりすると影響力が大きくそれが定説になってしまうので
問題です
ただし、レトリーブが曖昧な時に複数のディスクをバンバンと投げてしまうとレトリーブの精度に欠けディスタンスがうまくいかなくなってしまう危険性は
十分あります
冷静に考えてみましょう
ディスクドッグの基本はレトリーブ(持来)です
ディスタンスもフリーもここを基本動作として教えていくことになります
フリーは更に複数のディスクを使って様々な体勢でのキャッチやキャッチ後のディスクの処理(持ち帰るのか、その場にドロップするのか)を教えて
いくことになります
言わば、ディスタンスはフリースタイルのトリックの一つなんです
その一つのトリックだけをクローズアップさせて出来たのがディスタンス競技だと思いませんか?
だから心配はいりません
逆の場合のはよく見かけます
1枚のディスクでしか遊んだ経験ない犬の中には複数のディスクを拒否し、1枚に拘ってしまうといった例です
このような場合、少し時間が掛かるかもしれませんが少しずつ慣らしていけばなんとかなります
実際、ここを克服したチームがken.styleにいます
ここまで散々フリースタイルをお薦めする記事を書いてきましたが最終的には愛犬がどっちに向いているかが重要です
俊敏で、どの方向にも瞬時に対応できるような犬はフリー向きだし、直線的な動きが得意な犬はディスタンス向きだと言えます
ディスタンスな人達ってほぼディスタンスしかしないし、フリースタイルな人達もフリースタイルしか考えていない気がしません?
犬の個性で決めたらどうでしょう
そして、われわれ飼い主がどちらも出来るようにフリーとディスタンス、両方のスキルを磨いておいて犬のいいとこ伸ばしていきませんか?
2012年06月20日
ディスク考察
フライングディスクって色々な形や種類があって本当に面白いと思いませんか?
1970年代の後半だったと記憶していますが、確かNOVAという商品名のスポンジ製のディスクがコマーシャルで宣伝されブームとなりました。
以来、世間一般的にはあれほどのブームは起きていませんが、公園なんかに行くとたまに子供たちが中央に穴の開いたディスクで遊んでいるのは
よく見かける光景ですよね。
僕がディスクドッグを始めた時に手に入れたのがHero社製のファストバックの235。
このディスクはホームセンターのペットコーナーで購入出来たためにすぐに手に入れる事が出来ました。

このディスクは売られていたものではなくHero製アシュレイウィペットチャンピオンシップ記念ディスク。
犬になんとかキャッチさせることが出来るようになり競技会に参加するようになってエントリーするとディスクが付いてきました。
それがこちら


JFAでお馴染みの言わずと知れたWam-O社製のフリスビー。
上は職権乱用してシルク印刷でken.styleのロゴを印刷してみた物です。
下のディスクはサインが入っておりますが、これは杉山清貴さんのサインなんです!
だいすけさんの経営する居酒屋「庄八」にみえると言うので予めディスクを渡しておいてサインをいただいた物です。
杉山清貴さんもディスクにサインしたのは初めてかもしれません(笑)
会員になるとセールなんかで安く購入出来たためフリスビー生活が始まりました。
DDGameに参加すると
こちら

そうです初めて手にしたディスク、Heroのファストバックが付いてきます。
Wam-Oのファストバックのフリスビーと同じファストバックモデルですが若干形状が異なります。
ちなみに直径はどちらも235ミリ。
どこが違うかというと中央部の盛り上がりです。
Wam-Oのフリスビーの方が盛り上がりが大きい様です。
投げ比べてみるとわかりますがフリスビーの方がアンダーステイブル(右に傾く性質が強い)。
ぱっと見、ほとんど同じに見えますが微妙な形状な違いが飛行状態を大きく作用するのは驚きです。
そしてDDGameに参加して県外のお友達が出来ました。
そのお友達のお誘いでスカイハウンズ(現NDA)の大会にエントリーしました。
その時について来たのがこのディスク。

直径が225ミリとファストバックにピッタリと入るサイズ。
形も独特です。
現在NDAで使用さているのがこちら。

(SDC主宰、栄将男先生が2004年にスーパークラスでチャンピオンになられた時の記念ディスクです。)
Jディスクと呼ばれているディスクです。スカイハウンズ時代のものとは横から見るとこれまた微妙に違います。

(このJディスクは鹿児島のフリースタイラー、上野氏が2009フリースタイルチャンピオンになられた時の記念ディスク。)
このJディスクをあるじき使っていました。
ファストバックに比べると飛距離が出る事と、向かい風に強い気がします。
逆にディスクスピードが速いため追い風が難しく感じます。
そしてこのディスク知ってます?

(らぶ蔵パパからの頂き物です)
なんとこのディスクは初期のJFAで使われていたものだそうです。
大きさ形、Jディスクそっくり。っていうかスカイハウンズ時代のディスクとウリ二つなんです。
なんかビックリですよね。
次にこちら。

(このディスクもらぶ蔵パパからの頂き物! 中央部には無理を言って頂いたサインが)
これは犬用のものではなくヒューマン用なんですねぇ。
まず見た目がデカイ!!
持ったら重い!!!
いつもの癖でアングルつけて投げるとディスクが起きない!?
オーバーステーブル(左に傾く性質)のディスクなんです。よって上手にスローするにはフラットもしくはアンハイ気味に投げる必要があります。
今結構ハマってます。これ投げた後、ファストバック投げると気持ちいいんです!!!
そしてこの逸品。

(K9のテクニカルディレクター塚崎氏からの頂き物!)
メタルと書かれたフリスビー。
なんとこのフリスビーはですね、一万円で二枚しか買うことが出来ない高価なディスクなんだそうです。
何が凄いのってその精度が凄いんだそうです!
確かに平べったいガラスの上に置くと他の物は若干よじれていますが、メタルはぴたっと隙間なくくっついています。メタルって聞いたとき、
金属で出来ているとばかり思っていて現物見た時少し拍子抜けしましたがこの素材でこの精度にはビックリです。品番はFB6
現在出回っているフリスビーがFB11~12なのでもう手に入らないでしょうね。
もったいなくって投げれません(笑) どう飛ぶんでしょうねぇ?
最後はこのディスク。

今シーズンよりK9にエントリーするとついてくるディスクです。
215と呼ばれているディスクです。アメリカで生産されているHero社製のディスクなんだそうです。
Hero社は日本のメーカーなのにって?すみません理由はよくわかりません。
投げるとですね、癖がないんですねぇこれが!!!
その名の指す通り、直径215ミリで90グラム。
フリスビーが100グラムなので10グラム軽いんですけど、直径で2センチ小さいので持ってみると以外にずっしりとしている。
向かい風強いですね!!!
かと言ってホバリングの具合もいい。いい仕事してますって感じです!!!
様々なディスクを紹介しましたが、ほんと微妙な形状の違いでディスクの飛行特性ってこんなに違うものかって思ってしまいます。
以前は、フリスビーで競技に出てた時はフリスビー以外は努めて握らない様に心掛けていました。
またJディスクで競技に出ていた時期はJディスク以外は握らない様にしていました。
理由は、違う形状の物を投げてしまうと体が混乱してしまい、どのディスクも思うように投げれなくなると思っていたからです。
ところが最近、それが間違いである事が分かったのです。
様々なディスクを投げる事でディスクの持つ特性を読む、そして個々の特性に合わせたスローが出来た時って微妙な風の変化に合わせたスローが
出来るって確信しました。
向かい風が苦手とか追い風が苦手とか思っている人たちはとにかく色々なディスク投げてみてはいかがでしょうか?一気に上達するかも。
犬用のディスクは、ほぼアンダーステイブルなのでオーバーステイブルのヒューマン用がお薦めですね。極端に違う特性を持つディスクがいいんじゃないでしょうか。
どのディスクでもOKなK9では今後、風の状態などでディスクを投げ分けるといったプレーヤーが多くなるでしょうね。ディスクゴルフみたいな感じで
ディスク選びで勝敗を左右するといった他では味わえない競技色も見えてくるかもしれません。
kenBOSS
1970年代の後半だったと記憶していますが、確かNOVAという商品名のスポンジ製のディスクがコマーシャルで宣伝されブームとなりました。
以来、世間一般的にはあれほどのブームは起きていませんが、公園なんかに行くとたまに子供たちが中央に穴の開いたディスクで遊んでいるのは
よく見かける光景ですよね。
僕がディスクドッグを始めた時に手に入れたのがHero社製のファストバックの235。
このディスクはホームセンターのペットコーナーで購入出来たためにすぐに手に入れる事が出来ました。

このディスクは売られていたものではなくHero製アシュレイウィペットチャンピオンシップ記念ディスク。
犬になんとかキャッチさせることが出来るようになり競技会に参加するようになってエントリーするとディスクが付いてきました。
それがこちら


JFAでお馴染みの言わずと知れたWam-O社製のフリスビー。
上は職権乱用してシルク印刷でken.styleのロゴを印刷してみた物です。
下のディスクはサインが入っておりますが、これは杉山清貴さんのサインなんです!
だいすけさんの経営する居酒屋「庄八」にみえると言うので予めディスクを渡しておいてサインをいただいた物です。
杉山清貴さんもディスクにサインしたのは初めてかもしれません(笑)
会員になるとセールなんかで安く購入出来たためフリスビー生活が始まりました。
DDGameに参加すると
こちら

そうです初めて手にしたディスク、Heroのファストバックが付いてきます。
Wam-Oのファストバックのフリスビーと同じファストバックモデルですが若干形状が異なります。
ちなみに直径はどちらも235ミリ。
どこが違うかというと中央部の盛り上がりです。
Wam-Oのフリスビーの方が盛り上がりが大きい様です。
投げ比べてみるとわかりますがフリスビーの方がアンダーステイブル(右に傾く性質が強い)。
ぱっと見、ほとんど同じに見えますが微妙な形状な違いが飛行状態を大きく作用するのは驚きです。
そしてDDGameに参加して県外のお友達が出来ました。
そのお友達のお誘いでスカイハウンズ(現NDA)の大会にエントリーしました。
その時について来たのがこのディスク。

直径が225ミリとファストバックにピッタリと入るサイズ。
形も独特です。
現在NDAで使用さているのがこちら。

(SDC主宰、栄将男先生が2004年にスーパークラスでチャンピオンになられた時の記念ディスクです。)
Jディスクと呼ばれているディスクです。スカイハウンズ時代のものとは横から見るとこれまた微妙に違います。

(このJディスクは鹿児島のフリースタイラー、上野氏が2009フリースタイルチャンピオンになられた時の記念ディスク。)
このJディスクをあるじき使っていました。
ファストバックに比べると飛距離が出る事と、向かい風に強い気がします。
逆にディスクスピードが速いため追い風が難しく感じます。
そしてこのディスク知ってます?

(らぶ蔵パパからの頂き物です)
なんとこのディスクは初期のJFAで使われていたものだそうです。
大きさ形、Jディスクそっくり。っていうかスカイハウンズ時代のディスクとウリ二つなんです。
なんかビックリですよね。
次にこちら。

(このディスクもらぶ蔵パパからの頂き物! 中央部には無理を言って頂いたサインが)
これは犬用のものではなくヒューマン用なんですねぇ。
まず見た目がデカイ!!
持ったら重い!!!
いつもの癖でアングルつけて投げるとディスクが起きない!?
オーバーステーブル(左に傾く性質)のディスクなんです。よって上手にスローするにはフラットもしくはアンハイ気味に投げる必要があります。
今結構ハマってます。これ投げた後、ファストバック投げると気持ちいいんです!!!
そしてこの逸品。

(K9のテクニカルディレクター塚崎氏からの頂き物!)
メタルと書かれたフリスビー。
なんとこのフリスビーはですね、一万円で二枚しか買うことが出来ない高価なディスクなんだそうです。
何が凄いのってその精度が凄いんだそうです!
確かに平べったいガラスの上に置くと他の物は若干よじれていますが、メタルはぴたっと隙間なくくっついています。メタルって聞いたとき、
金属で出来ているとばかり思っていて現物見た時少し拍子抜けしましたがこの素材でこの精度にはビックリです。品番はFB6
現在出回っているフリスビーがFB11~12なのでもう手に入らないでしょうね。
もったいなくって投げれません(笑) どう飛ぶんでしょうねぇ?
最後はこのディスク。

今シーズンよりK9にエントリーするとついてくるディスクです。
215と呼ばれているディスクです。アメリカで生産されているHero社製のディスクなんだそうです。
Hero社は日本のメーカーなのにって?すみません理由はよくわかりません。
投げるとですね、癖がないんですねぇこれが!!!
その名の指す通り、直径215ミリで90グラム。
フリスビーが100グラムなので10グラム軽いんですけど、直径で2センチ小さいので持ってみると以外にずっしりとしている。
向かい風強いですね!!!
かと言ってホバリングの具合もいい。いい仕事してますって感じです!!!
様々なディスクを紹介しましたが、ほんと微妙な形状の違いでディスクの飛行特性ってこんなに違うものかって思ってしまいます。
以前は、フリスビーで競技に出てた時はフリスビー以外は努めて握らない様に心掛けていました。
またJディスクで競技に出ていた時期はJディスク以外は握らない様にしていました。
理由は、違う形状の物を投げてしまうと体が混乱してしまい、どのディスクも思うように投げれなくなると思っていたからです。
ところが最近、それが間違いである事が分かったのです。
様々なディスクを投げる事でディスクの持つ特性を読む、そして個々の特性に合わせたスローが出来た時って微妙な風の変化に合わせたスローが
出来るって確信しました。
向かい風が苦手とか追い風が苦手とか思っている人たちはとにかく色々なディスク投げてみてはいかがでしょうか?一気に上達するかも。
犬用のディスクは、ほぼアンダーステイブルなのでオーバーステイブルのヒューマン用がお薦めですね。極端に違う特性を持つディスクがいいんじゃないでしょうか。
どのディスクでもOKなK9では今後、風の状態などでディスクを投げ分けるといったプレーヤーが多くなるでしょうね。ディスクゴルフみたいな感じで
ディスク選びで勝敗を左右するといった他では味わえない競技色も見えてくるかもしれません。
kenBOSS
2011年11月12日
リーダーシップ
久々にうんちくでもたれてみたいと思います(笑)
ディスクドッグであろうと、家庭のペット、作業犬、使役犬であろうと飼い主、ハンドラーのリーダーシップは必要不可欠なのは言うまでもありません。
さて、皆さんはリーダーシップを発揮できているでしょうか?
リーダーシップを発揮出来ている人の犬は飼い主さんへの注目度が違う様に思います。
常に飼い主の一挙手一投足を見逃さまいと注目しています。
例えば、ディスタンスの受け渡しが出来ないとか、フリーの簡単なトリックが出来ないとか言った場合には犬との関係を見直して見てはいかがでしょうか?
最近、全てはここの部分に集約されているように思うのです。
しつけの本などには、必ず犬のリーダーにならなければならないとか、絶対的な存在にならなくてはいけないというニュアンスの文章が書かれています。
僕自身もご多分に漏れずその通りだと思っていますが、リーダーにならなきゃいけないと思った瞬間に多くの人が犬に対して威圧的な態度を取ったり、高慢な姿勢で犬に色々と押し付けてしまいます。(以前は僕もそうした時期を過ごしました)
「群れのリーダー」という言葉がどうしても我々人間には腕力の象徴というような受け取り方になってしまうようです。
また反対に犬に媚を売って犬からの信頼を得ようとする人達もいます。
このタイプの人達は犬が悪い事をしても叱ることができず、犬に対して猫可愛がりをします。
おじいちゃんやおばあちゃんが孫を溺愛する行動によく似ています。
犬は大変賢い動物なので、おやつやおもちゃなどでつられると都合良くそっちになびく術も知っています。
2つの極端な例を挙げてみましたが、これではリーダーシップは築けません。
では、犬達からの信頼はどのようにしたら得られるのでしょうか?
僕はこう思います。
犬と向き合う時には人間的な思考を捨てて同じ目線でぶつかり合う事。
文字にしてみると何かとても変ですが・・・
ようは、犬に認められて初めてリーダーの座に就く事が出来るのです。
優しさと厳しさをもって犬と接する事が重要です。
大事なのは褒め方と叱り方で、けして甘やかし方と怒り方ではありません。
褒め方ですが、子犬の頃はともかく成犬になればタイミング良くあっさりがいいです。
出したコマンドに反応した直後、またはその行動を起こす瞬間がベストです。
褒め慣れていない人は、褒め忘れたり褒めるタイミングが遅すぎたりで犬に伝わらないことが多いように思います。
次に叱り方です。
僕の場合、犬に叱る場面というのはほとんどありません。
ディスクのトレーニングでの失敗は叱る所ではないし、むしろ叱るのはマイナスだとさえ思っています。
ですから、失敗に対しては叱りません。
ディスクの競技会などではたまに、言う事を聞かないからといって大声で叱りつけたりディスクで叩く人を見かけた事もありますが、そんなのは愚のコッチョです。考えて見て下さい、ミスをおかしているのは我々人間側にあることがほとんどです。
注意を促すことはよくあります。
「それ違うよ」とか「イケナイ」や「ノー」を使います。
あくまで注意を促すコマンドなので威圧的には言いません。これで十分に伝わります。
叱る場面があるとすれば、人や犬に攻撃をしかけるもしくは攻撃をしようとした時くらいでしょうか。
この時だけは犬の言い分は聞けません。勿論、喧嘩を買う事も許しません。
一撃が必要になります。効き目のある一撃です
仮に人に噛み付いたとなると処分される危険性があります。そうさせないためには必要な事だと思っています。
理想は犬から見て、頼りがいがあって、この人と居たらいつも楽しくて安心できる大好きな人。
そんなリーダー目指していきましょう!!

ラブちゃん入れるの忘れてた!
ディスクドッグであろうと、家庭のペット、作業犬、使役犬であろうと飼い主、ハンドラーのリーダーシップは必要不可欠なのは言うまでもありません。
さて、皆さんはリーダーシップを発揮できているでしょうか?
リーダーシップを発揮出来ている人の犬は飼い主さんへの注目度が違う様に思います。
常に飼い主の一挙手一投足を見逃さまいと注目しています。
例えば、ディスタンスの受け渡しが出来ないとか、フリーの簡単なトリックが出来ないとか言った場合には犬との関係を見直して見てはいかがでしょうか?
最近、全てはここの部分に集約されているように思うのです。
しつけの本などには、必ず犬のリーダーにならなければならないとか、絶対的な存在にならなくてはいけないというニュアンスの文章が書かれています。
僕自身もご多分に漏れずその通りだと思っていますが、リーダーにならなきゃいけないと思った瞬間に多くの人が犬に対して威圧的な態度を取ったり、高慢な姿勢で犬に色々と押し付けてしまいます。(以前は僕もそうした時期を過ごしました)
「群れのリーダー」という言葉がどうしても我々人間には腕力の象徴というような受け取り方になってしまうようです。
また反対に犬に媚を売って犬からの信頼を得ようとする人達もいます。
このタイプの人達は犬が悪い事をしても叱ることができず、犬に対して猫可愛がりをします。
おじいちゃんやおばあちゃんが孫を溺愛する行動によく似ています。
犬は大変賢い動物なので、おやつやおもちゃなどでつられると都合良くそっちになびく術も知っています。
2つの極端な例を挙げてみましたが、これではリーダーシップは築けません。
では、犬達からの信頼はどのようにしたら得られるのでしょうか?
僕はこう思います。
犬と向き合う時には人間的な思考を捨てて同じ目線でぶつかり合う事。
文字にしてみると何かとても変ですが・・・
ようは、犬に認められて初めてリーダーの座に就く事が出来るのです。
優しさと厳しさをもって犬と接する事が重要です。
大事なのは褒め方と叱り方で、けして甘やかし方と怒り方ではありません。
褒め方ですが、子犬の頃はともかく成犬になればタイミング良くあっさりがいいです。
出したコマンドに反応した直後、またはその行動を起こす瞬間がベストです。
褒め慣れていない人は、褒め忘れたり褒めるタイミングが遅すぎたりで犬に伝わらないことが多いように思います。
次に叱り方です。
僕の場合、犬に叱る場面というのはほとんどありません。
ディスクのトレーニングでの失敗は叱る所ではないし、むしろ叱るのはマイナスだとさえ思っています。
ですから、失敗に対しては叱りません。
ディスクの競技会などではたまに、言う事を聞かないからといって大声で叱りつけたりディスクで叩く人を見かけた事もありますが、そんなのは愚のコッチョです。考えて見て下さい、ミスをおかしているのは我々人間側にあることがほとんどです。
注意を促すことはよくあります。
「それ違うよ」とか「イケナイ」や「ノー」を使います。
あくまで注意を促すコマンドなので威圧的には言いません。これで十分に伝わります。
叱る場面があるとすれば、人や犬に攻撃をしかけるもしくは攻撃をしようとした時くらいでしょうか。
この時だけは犬の言い分は聞けません。勿論、喧嘩を買う事も許しません。
一撃が必要になります。効き目のある一撃です

仮に人に噛み付いたとなると処分される危険性があります。そうさせないためには必要な事だと思っています。
理想は犬から見て、頼りがいがあって、この人と居たらいつも楽しくて安心できる大好きな人。
そんなリーダー目指していきましょう!!

ラブちゃん入れるの忘れてた!
2011年08月10日
逆教法!?
何それ?
僕が作った造語です(笑)
以前、サークルのリーダーを任され現在はディスクドッグチームのBOSSを務めています
悲しい事にその間には、多くの人達がディスクドッグの門を叩きそして去って行ってしまいました
正直、ディスクドッグって遊び半分で出来てしまう場合もありますが、そこに情熱と犬を理解する気持ちがないとそれ以上のレベルにはなかなかたどり着けない事も事実です
ただ、ディスクドッグに興味を持ってもらった全ての人達に楽しんでもらいたいという気持ちがあります
しかし、自分自身の経験や先人達のノウハウを伝えようにもなかなか上手く伝える事は難しいと常々感じています
実際、ディスクドッグを育てていくためのマニュアル化は難しいのです
理由は、犬種による習性の違いや同じ犬種であっても個体差というものが存在するため、ここには経験や多くの知識が必要になります
マニュアル化してしまうとイレギュラーな事が起こってしまうとそこに大きな壁が立ちはだかってしまいます
電気製品の取り扱い説明書のようにはいかないのです
そこでです!
kenBOSSが提案する「逆教法」の出番になります(この時点で呼び戻しが出来ている事が前提です)

例えば、ディスクドッグの基本となるディスタンスを教えていくときに初心者の人達はまず間違いなくディスクをスローイングしてしまいます
まず、ここに大きな間違いがあります
犬はその本能により特に教えることもなくあっさりディスクを追いかけていくと思われますが、その後のディスクの処理が解らず犬もまごついてしまいます
そしてこの時点で人と犬との距離的な間隔が空いてしまっているので迅速な犬への対応に時間差が生じてしまいます
よって犬に理解しにくいものとなってしまうものと思われます
ディスタンスって、①ディスクのスローイング ②犬によるキャッチング ③受け渡し 以上この三つの動作を繰り返すことで成り立っています
ですからこれを①②③の順番通りに教えてしまうから犬にとって理解しにくくなってしまうと思います
③受け渡し ②キャッチング ①追わせる(スロー)逆の順番でそれぞれの動作をきっちり教えていくことで犬が認識しやすくなります
逆から教えていくので「逆教法」です(笑)
犬に上手に教えている人達って無意識あるいは意識的に「逆教法」使ってます(確信してます)
しかし、今まであまりクローズアップされなかったことが不思議でなりません
フリースタイルの色々なトリックも「逆教法」によって教えていきます
より複雑な動き程この方法が功を奏します
「逆教法」は、一つの流れを分割し各パートの動きの最後から準に教えていきます
ドッグキャッチであれば抱っこの状態で褒めの言葉をかけてあげたり(UP GOOD!!)ご褒美としてトリーツを与えます
CONNIEで行ったフットプラントもこの方法でクリヤー出来ました(詳しくはこのブログのバックページを)
フリースタイルにはたくさんの技(トリック)がありますが、各トリックのマスターさせる順番も大切だと思っています
具体的にはオーバー系のトリックは、○○をマスターさせた後にしないと○○が難しくなってしまうとかです(全然具体的じゃないし)
個人的理論なので○○としました
ただ、理想とするプレーや将来やってみたいトリックなどがあればそれを想定した設計図のようなものを事前に作り上げておくべきだと思っています
例えが良いかどうか解りませんが、車のプラモデルを作る時に説明書を無視してしまい、先にボディーとシャーシを接着してしまった結果シートやダッシュボードの部品が取り付けられなかったという感じです
ディスクドッグのトレーニングにはとにかく綿密な計算がかかせません!!
多くの人達が「逆教法」を意識してトレーニングに臨む事により喜びの声が聞けたらいいな〜
合い言葉は、「逆教法」です!!!
kenBOSS
僕が作った造語です(笑)
以前、サークルのリーダーを任され現在はディスクドッグチームのBOSSを務めています
悲しい事にその間には、多くの人達がディスクドッグの門を叩きそして去って行ってしまいました
正直、ディスクドッグって遊び半分で出来てしまう場合もありますが、そこに情熱と犬を理解する気持ちがないとそれ以上のレベルにはなかなかたどり着けない事も事実です
ただ、ディスクドッグに興味を持ってもらった全ての人達に楽しんでもらいたいという気持ちがあります
しかし、自分自身の経験や先人達のノウハウを伝えようにもなかなか上手く伝える事は難しいと常々感じています
実際、ディスクドッグを育てていくためのマニュアル化は難しいのです
理由は、犬種による習性の違いや同じ犬種であっても個体差というものが存在するため、ここには経験や多くの知識が必要になります
マニュアル化してしまうとイレギュラーな事が起こってしまうとそこに大きな壁が立ちはだかってしまいます
電気製品の取り扱い説明書のようにはいかないのです
そこでです!
kenBOSSが提案する「逆教法」の出番になります(この時点で呼び戻しが出来ている事が前提です)

例えば、ディスクドッグの基本となるディスタンスを教えていくときに初心者の人達はまず間違いなくディスクをスローイングしてしまいます
まず、ここに大きな間違いがあります
犬はその本能により特に教えることもなくあっさりディスクを追いかけていくと思われますが、その後のディスクの処理が解らず犬もまごついてしまいます
そしてこの時点で人と犬との距離的な間隔が空いてしまっているので迅速な犬への対応に時間差が生じてしまいます
よって犬に理解しにくいものとなってしまうものと思われます
ディスタンスって、①ディスクのスローイング ②犬によるキャッチング ③受け渡し 以上この三つの動作を繰り返すことで成り立っています
ですからこれを①②③の順番通りに教えてしまうから犬にとって理解しにくくなってしまうと思います
③受け渡し ②キャッチング ①追わせる(スロー)逆の順番でそれぞれの動作をきっちり教えていくことで犬が認識しやすくなります
逆から教えていくので「逆教法」です(笑)
犬に上手に教えている人達って無意識あるいは意識的に「逆教法」使ってます(確信してます)
しかし、今まであまりクローズアップされなかったことが不思議でなりません
フリースタイルの色々なトリックも「逆教法」によって教えていきます
より複雑な動き程この方法が功を奏します
「逆教法」は、一つの流れを分割し各パートの動きの最後から準に教えていきます
ドッグキャッチであれば抱っこの状態で褒めの言葉をかけてあげたり(UP GOOD!!)ご褒美としてトリーツを与えます
CONNIEで行ったフットプラントもこの方法でクリヤー出来ました(詳しくはこのブログのバックページを)
フリースタイルにはたくさんの技(トリック)がありますが、各トリックのマスターさせる順番も大切だと思っています
具体的にはオーバー系のトリックは、○○をマスターさせた後にしないと○○が難しくなってしまうとかです(全然具体的じゃないし)
個人的理論なので○○としました
ただ、理想とするプレーや将来やってみたいトリックなどがあればそれを想定した設計図のようなものを事前に作り上げておくべきだと思っています
例えが良いかどうか解りませんが、車のプラモデルを作る時に説明書を無視してしまい、先にボディーとシャーシを接着してしまった結果シートやダッシュボードの部品が取り付けられなかったという感じです
ディスクドッグのトレーニングにはとにかく綿密な計算がかかせません!!
多くの人達が「逆教法」を意識してトレーニングに臨む事により喜びの声が聞けたらいいな〜
合い言葉は、「逆教法」です!!!
kenBOSS
2011年07月24日
松風レトリーブ
まんまるおデブの「松風!!」です!
毎日たくさん食べてすくすく育っております
レトリーブの動画をアップしておりますが正直まだ本腰入れて教えてはいません
これは「松風!!」が勝手にというか自分で考えてディスクで遊んでいる光景です
何言ってるの?と思う方もいると思うのでちょっとうんちくたれてみたいと思います
ただいま「松風!!」生後10週を迎えたところです
今「松風!!」が学ぶべきことは、ディスクのテクニカル的英才教育ではなくまだその前段階、人や他の犬に対してフレンドリーになること、そして様々な環境への適応能力なのです
いま気を付けていることは今経験させなければならない事を積極的に経験させ、経験させてはならない事(トラウマ)を極力回避する事に全力を傾けています
話を元に戻しますが、上の動画は近所のグラウンドにお散歩に出掛けた時たまたま車に積んであったディスクでローラーしてみた所なんです
一見、この月齢でなんて思ってしまいそうですが、ここにディスクドッグの落とし穴があるのです
それは、「松風!!」が勝手に考えてやっているところにあります
時期が来たらきっちりレトリーブを教える必要があります
そうしないと今度はこちらの意に沿わないことを自分で考えてやるようになる危険性をはらんでいるからです
あわてない あわてない 一休み 一休み
kenBOSS
2011年06月03日
DISC DOG LIBRARY
何か新しい事をする時にみんなはどうするのかな?
今はインターネットがあって調べものなんかにはとても便利ですよね!
最近でこそ、パソコンを開けるようになりましたがアナログの僕はやっぱり本で知識を深める方が性に合うようです。
ぼくがディスクドッグを始めた今から約9年前、最初に購入した本がこれ。
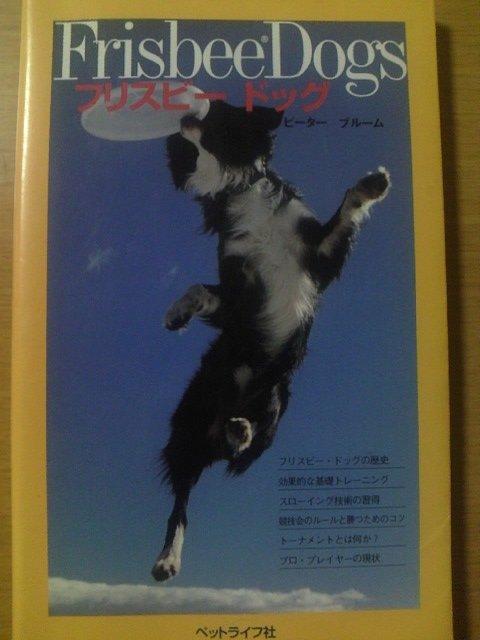
ディスクドッグを日本に紹介したピーターブルームさん著の書籍です。
今から16年前に初版が発行されています。僕の持っているものが第5刷と書かれてあるのでかなりの発行部数だと思います。
それはそのはず、当時ディスクドッグのHOW TO本はこの本しかなくディスクドッグの教科書だったと推測されます。
ディスクドッグの先輩の方達のバイブルだったに違いありません!
もちろん僕にとってもバイブルです。いまでもよく読み返す事があります。
次に購入したのがこれ。
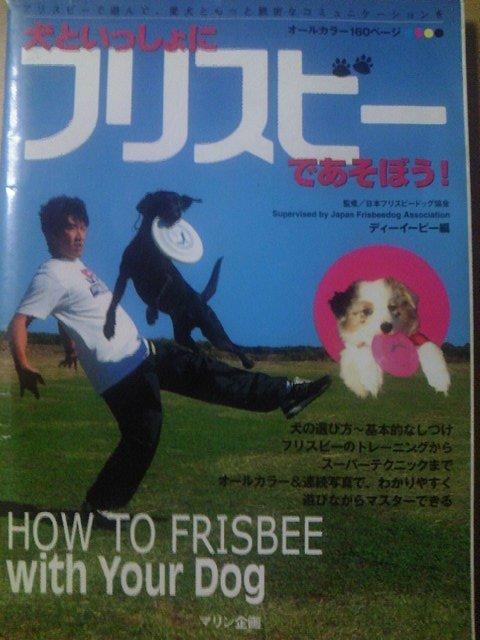
2004年の5月発売と同時に手に入れた本です!
監修はJFAで今でも書店に並んでいるのを見かけます。
オールカラーの豪華な本で、そこに出ているモデルの方達も豪華です。
フリースタイルの一時代を築いた人達が様々なトリックを親切に解説してあります。
とにかく必見です!
続いて3〜4年前、大分市内の古本屋さんで見つけたお宝がこれ。
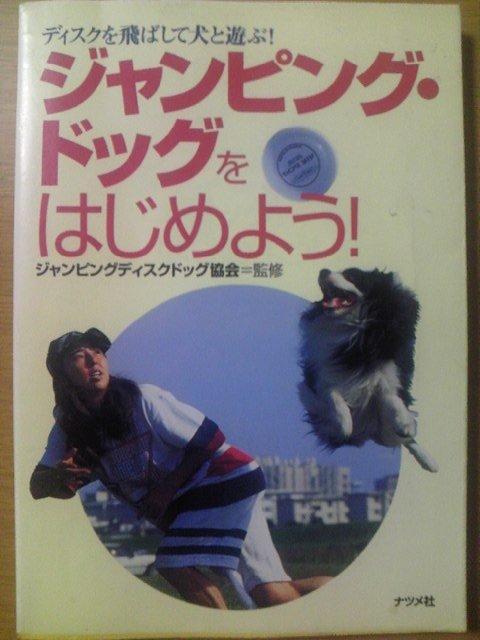
初版の発行が1997年だから14年前。日本最古のディスクドッグHOW TO本?
日本のディスクドッグ史に残る逸品かもしれません!これを今購入するのは難しいのではないでしょうか?
表紙の写真の方は、2005年の5月大分の日田市で行われたD*DGAMEにデモンストレーションに来てくれたNPA代表の方です。
ピーターの本は、言い回しがもろ英語を訳してるって感じがありありでちょっと読みにくいのですが、こちらは普通にわかりやすい。
内容も当時としてはセンセーショナルを引き起こしたものと思われます。
忘れてはいけないのがこの逸冊・・・いえいえ一冊でした(汗)
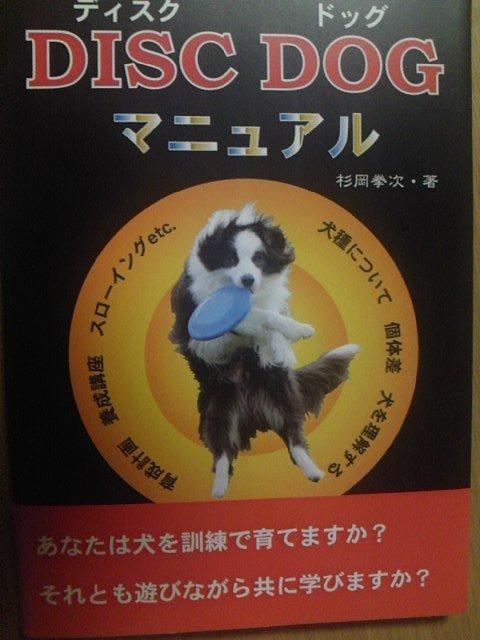
第一刷は2007年9月なのでもう4年が経ちます。ちなみにまだ残っているので二刷の予定もありません(汗)
以前サークルのお世話していた頃、月に1、2度の練習会の短い時間にノウハウを伝える事の難しさを実感することがたくさんありました。
まごまごしてる内に犬は月例を重ね、修正が難しくなってくる。上手くいかなくなって来ると飼い主さんも足が遠のいて行く。
よし、マニアルを作ろう!って簡単の気持ちで仕事の合間をぬって約1ヶ月で原稿を書き上げた本です。
当初、手書きのコピーみたいなものでって考えていたのですが少し欲をだして印刷機に掛けちゃいました。
仲間の取り計らいで書店にも並んだ時期もありました。
上の3冊と違う所は、全くフリースタイルの事には触れてない点です。触れてないというか触れる事が出来なかったんです。
当時、フリー出来なかったんです(大笑)
でもね、内容は自分でいうのも何ですがいいですよ。時間が経ってよくこんなの書けたな〜って思います。自分で言うなって
kenBOSS
今はインターネットがあって調べものなんかにはとても便利ですよね!
最近でこそ、パソコンを開けるようになりましたがアナログの僕はやっぱり本で知識を深める方が性に合うようです。
ぼくがディスクドッグを始めた今から約9年前、最初に購入した本がこれ。
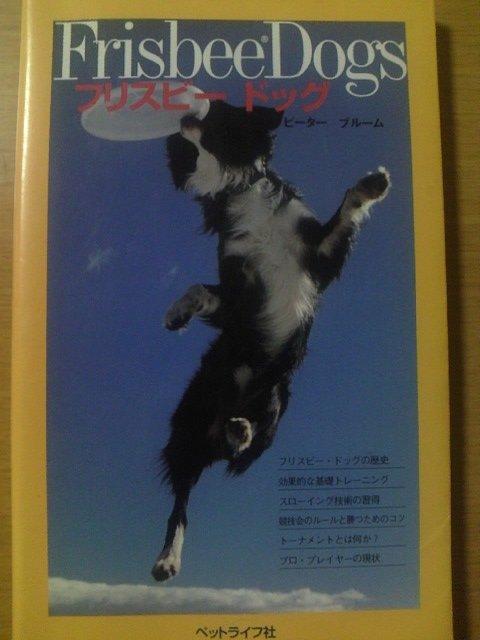
ディスクドッグを日本に紹介したピーターブルームさん著の書籍です。
今から16年前に初版が発行されています。僕の持っているものが第5刷と書かれてあるのでかなりの発行部数だと思います。
それはそのはず、当時ディスクドッグのHOW TO本はこの本しかなくディスクドッグの教科書だったと推測されます。
ディスクドッグの先輩の方達のバイブルだったに違いありません!
もちろん僕にとってもバイブルです。いまでもよく読み返す事があります。
次に購入したのがこれ。
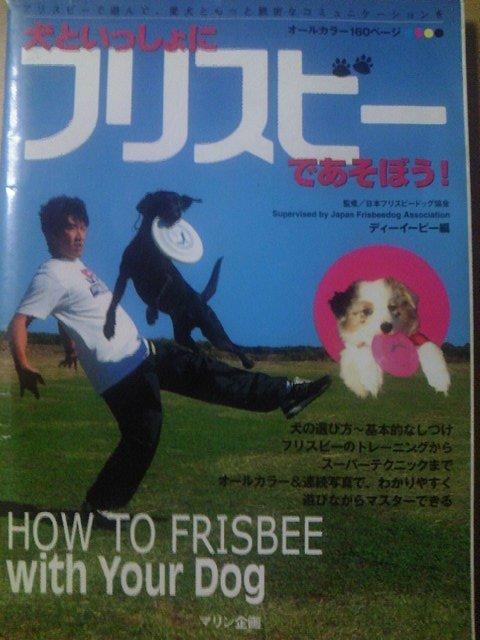
2004年の5月発売と同時に手に入れた本です!
監修はJFAで今でも書店に並んでいるのを見かけます。
オールカラーの豪華な本で、そこに出ているモデルの方達も豪華です。
フリースタイルの一時代を築いた人達が様々なトリックを親切に解説してあります。
とにかく必見です!
続いて3〜4年前、大分市内の古本屋さんで見つけたお宝がこれ。
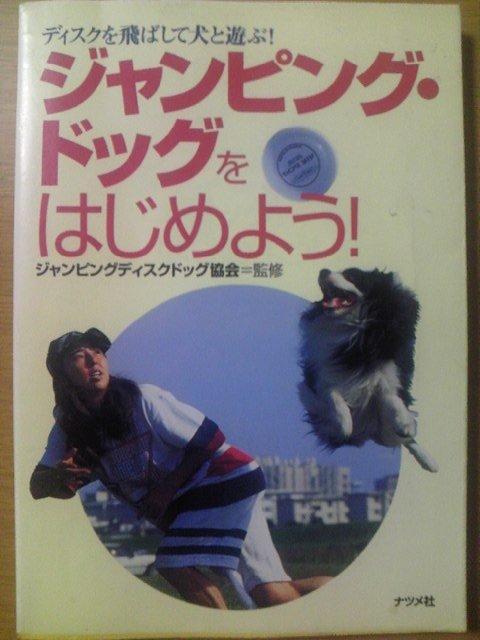
初版の発行が1997年だから14年前。日本最古のディスクドッグHOW TO本?
日本のディスクドッグ史に残る逸品かもしれません!これを今購入するのは難しいのではないでしょうか?
表紙の写真の方は、2005年の5月大分の日田市で行われたD*DGAMEにデモンストレーションに来てくれたNPA代表の方です。
ピーターの本は、言い回しがもろ英語を訳してるって感じがありありでちょっと読みにくいのですが、こちらは普通にわかりやすい。
内容も当時としてはセンセーショナルを引き起こしたものと思われます。
忘れてはいけないのがこの逸冊・・・いえいえ一冊でした(汗)
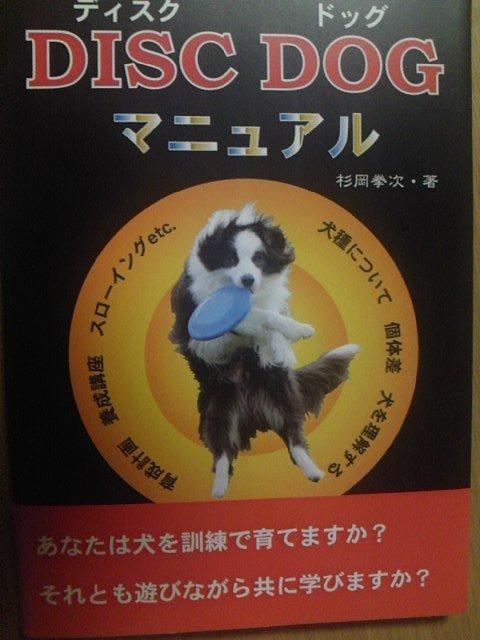
第一刷は2007年9月なのでもう4年が経ちます。ちなみにまだ残っているので二刷の予定もありません(汗)
以前サークルのお世話していた頃、月に1、2度の練習会の短い時間にノウハウを伝える事の難しさを実感することがたくさんありました。
まごまごしてる内に犬は月例を重ね、修正が難しくなってくる。上手くいかなくなって来ると飼い主さんも足が遠のいて行く。
よし、マニアルを作ろう!って簡単の気持ちで仕事の合間をぬって約1ヶ月で原稿を書き上げた本です。
当初、手書きのコピーみたいなものでって考えていたのですが少し欲をだして印刷機に掛けちゃいました。
仲間の取り計らいで書店にも並んだ時期もありました。
上の3冊と違う所は、全くフリースタイルの事には触れてない点です。触れてないというか触れる事が出来なかったんです。
当時、フリー出来なかったんです(大笑)
でもね、内容は自分でいうのも何ですがいいですよ。時間が経ってよくこんなの書けたな〜って思います。自分で言うなって
kenBOSS






